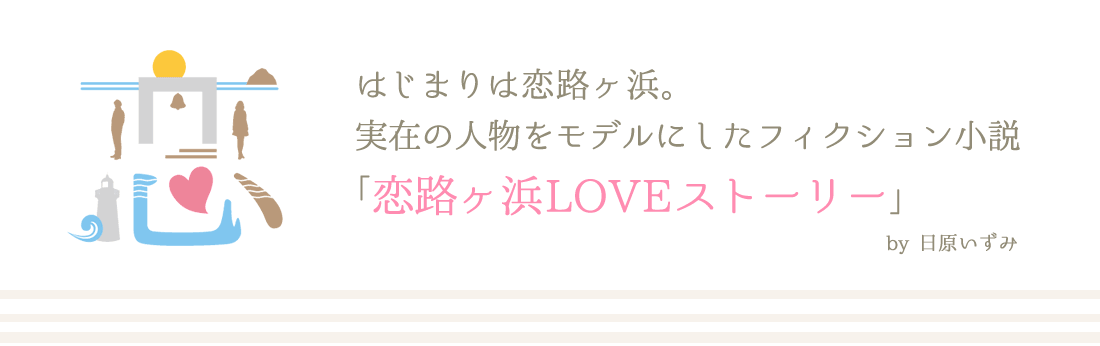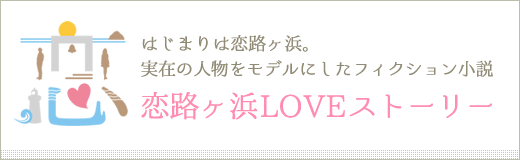遠距離恋愛は、会えない間さみしくて、会える時はひたすらうれしくて楽しい。
お互いもっと一緒にいたいと思うようになり、
3月に、大阪でみんなで行ったいちご狩りの次の日に、彼女のご両親との話の流れの中で
「いずれ、志寿香さんに田原に引っ越して来てもらおうかと考えています」と伝えた。
「結婚」という言葉には触れなかったけれど、もちろん結婚を意識してのことで勇気が要った。
ご両親はにこやかにうなずいてくれていた。
4月に東京へ一人で戻り、家族で焼き肉を食べに行った時に、ぼくが彼女について、
「いずれ田原に来てもらおうと思う」と話したら、母が「ちゃんとした形にしなくていいの?」と心配した。
志寿香と二人で一緒に生きていきたいと思うようになったものの、
具体的にいつ結婚しようとかは考えてなかったけれど、親の意見を受けて、ちゃんとした形=結婚も考え始めた。
毎日の電話で自分や親たちの気持ちを報告し合い、
5月に、東京と大阪の間の名古屋で両家が初めて顔を合わせることとなった。
偶然だけど、その日は、つき合って300日目の大安の日だ。

ぼくは、具体的にやりたいことを準備しながらも、3月に農業研修生期間を終え、
あちこちの農家のバイトを掛け持ちしているような状態。
こんな頼りない状態のぼくが、「結婚」を口にするのは
志寿香や志寿香のご両親に申し訳なくてためらわれた。
それなのに、大阪で初めて会った時も、今回の名古屋でも、
志寿香のご両親は、ぼく自身やぼくの夢を受け入れてくれた。
うちの親は、「本当にこの子でいいでしょうか?」と心配を口にしたけれど、
まさに百聞は一見にしかずというか、ぼくの親も志寿香のご両親を見て安心したし、
志寿香のご両親もぼくの親を見て安心してくれた様子だった。
お互い、東京と大阪といった、全く違う土地や文化で過ごしているのに、
不思議と似たような空気感がある。
想像以上に和やかな、初顔合わせの場だった。

のぞみに乗って大阪へ帰る志寿香親子を見送り、自分の両親をのぞみに乗せて、
ぼくは、ちょうど豊橋で停まるひかりがあったので、それに乗った。
豊橋から車を走らせ、一人渥美半島へ戻る。
「ああ、帰ってきたなあ」と安堵している自分に気づいた。
いつ頃からか、確かにぼくは、この場所をホームだと思うようになっている。
灯りの少ない夜道を、さらに灯りの減る方向へ向かいながら、
にぎやかな名古屋での食事の席を思い出す。
志寿香のまっすぐな目。
その志寿香をぼくに委ねようとしてくれるご両親の目。
ぼくをこれまで育ててくれた両親。
ぼくを信じてくれる人たち・・・
思わず涙ぐみながら、志寿香のことを、絶対に幸せにしようと思った。